お電話でのお問い合わせ
EDUBALでは、海外在住の生徒様ならではのお悩みと真摯に向き合い、指導させていただきます。
03-6756-8620
電話受付 平日10:00~19:00 (日本時間)
EDUBALでは、海外在住の生徒様ならではのお悩みと真摯に向き合い、指導させていただきます。
03-6756-8620
電話受付 平日10:00~19:00 (日本時間)
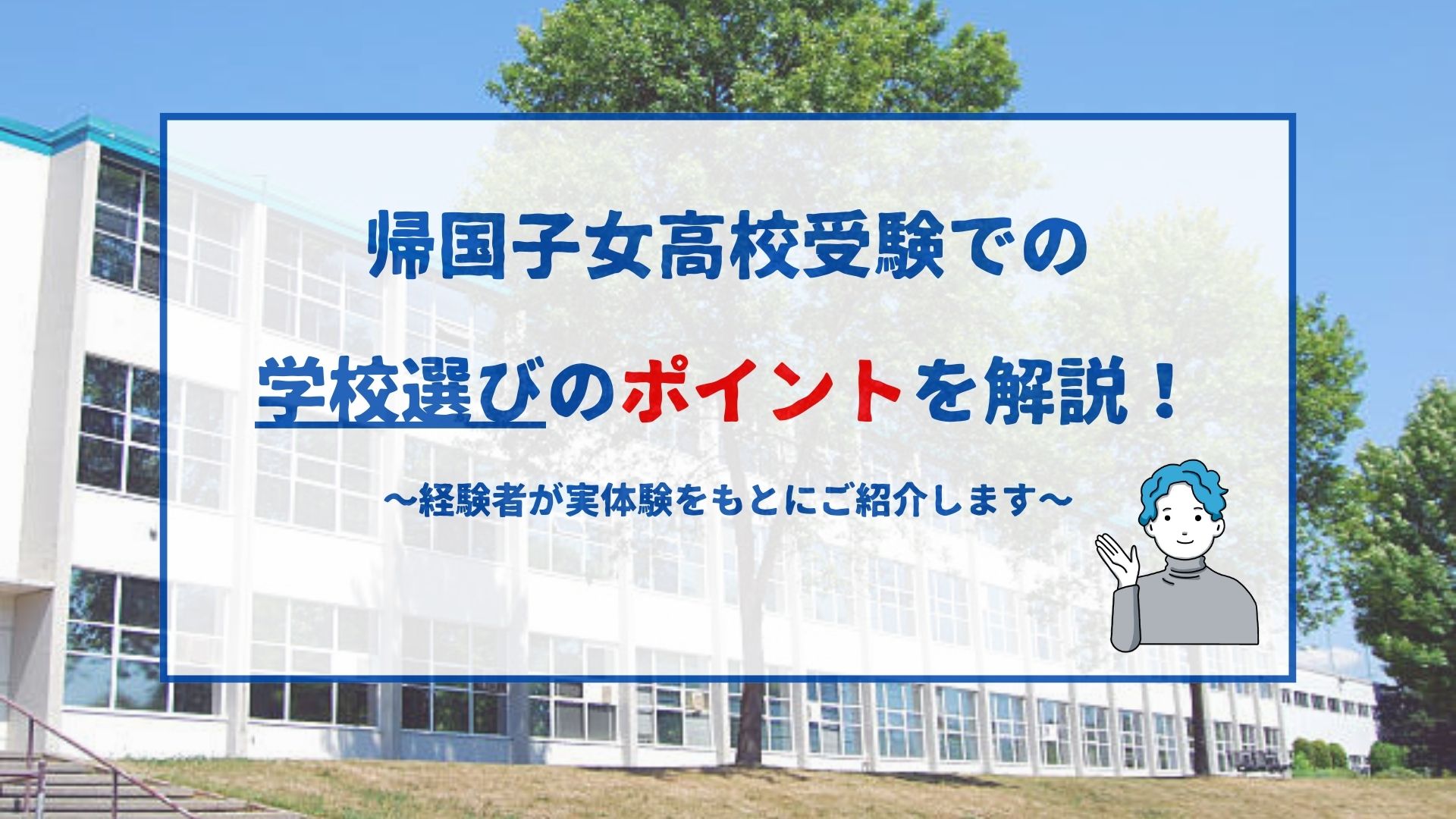
受験を控えるご家庭が初めにぶつかる壁として、学校選びが挙げられます。何を軸にして学校を選ぶべきか分からない…とお困りのご家庭が多いと思います。
そこで本記事では、高校受験を実際に経験した帰国子女の筆者が学校選びのポイントをご紹介します!
必ず考慮すべき点から必要があれば考慮しても良い点まで幅広く解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください!
.
一般的には、中学3年生(受験生)になったタイミングで志望校が決まっていると良いです。
受験本番の1年前は早すぎるのでは?とお考えの方もいると思いますが、この時期に志望校が決まっていると、本番までの1年間の過ごし方や学習計画を考えることができ、志望校合格への最適ルートを練ることができます。
学校によって受験方式(海外・オンライン会場の有無)や試験時期が異なるため、帰国のタイミングを早い段階から考えられるのも大きなメリットです。
また帰国子女高校受験は、学校によっては11月頃から受験がスタートします。この場合、進級のタイミングで志望校を決定しても本番まで半年ほどしか猶予がないため、早い段階での志望校決定が重要になります。
志望校決定については上記の時期が理想ですが、どうしてもそれには間に合わない…というご家庭も多いと思います。
そこで、遅くてもいつまでに決めるべきかをお伝えすると、それは中学3年生の夏です。
受験生の大半は夏頃から各自の志望校の過去問を解いていき、各校の傾向を見つけながら対策していきます。そのため、夏までに志望校が定まっていないと、本来過去問演習を通して志望校対策を進めていく時期にそれができないのです。
多くの学校は長期休み中にオープンキャンパスや学校説明会を行っており、受験生が志望校を決定する上で大きな手助けとなっています。海外駐在中の帰国子女がそれらに参加するのは難しいと思いますが、一時帰国の機会があれば、ぜひそれらに参加し学校の理解を深めてみてください。
.
帰国子女が学校選びにおいて必ず考慮すべき点の1つが、帰国子女の受け入れの有無、つまり帰国子女として受験できるかです。
帰国子女受験では、特定科目の免除や加点などがあり、帰国子女の日本の学習における遅れや偏り、さらには強みである語学力が考慮されたものになります。各々の得意・苦手科目にもよりますが、一般的には帰国子女は帰国子女受験の方が相性が良いと言われています。
そのため、帰国子女として受験できるかは事前に必ずチェックしておきましょう。
海外滞在年数は、ほとんどの学校で採用されている帰国子女の受験資格の1つです。
「海外に何年住んでいたか」によって、帰国子女として認められるかが決まります。学校によっては、継続して◯年/累計で◯年などの指定があります。
滞在年数の目安は2年ほどですが、これは学校によって異なるため、お子様が満たしている学校を選ぶようにしてください。
いつ帰国したかが問われるケースも多々あります。
学校によっては、帰国から1年以内に受験することというような条件を設けている場合があり、これを満たさないと帰国子女として認定されません。
そのため、条件を満たせる学校を選ぶか、受験校によって帰国時期を決定するようにしてください。
帰国子女が意外と引っかかってしまう条件に、「保護者の元から通学できるか」というものがあります。
帰国子女がいるご家庭に多く見られるのが、子供だけ高校入学のタイミングで帰国し、しばらくの間は知り合いや親戚の元から通学するというケースです。
保護者の元から通学できない場合は受験を認めないとしている学校もあるため、保護者と子供で帰国時期が異なる場合は、入学後に保護者との同居が求められない学校を選びましょう。
.
受験科目に焦点を当て志望校選びをする方は多いです。特に帰国子女の場合、得意科目・苦手科目の差が顕著のため、この傾向は強くなります。
高校受験において受験科目は学校によって様々で、英語・国語・数学の3教科のケースやそれに理科・社会を加えた5科目のケース、さらには筆記試験に加え面接や作文などが課されるケースもあります。
多くの学校では公式HPや問題集等で過去問を公開しているため、お子様の試験との相性を考慮して学校選びを行ってみるのも1つの手でしょう。
一般的には高校受験は1〜2月に実施されることが多いですが、帰国子女受験は11月頃から始まる学校もあります。
このように受験時期も学校によって異なるため、◯月までは帰国できない…などのご事情があるご家庭は、受験時期で絞ると学校選びが捗るかもしれません。
学校によっては海外に受験会場を設けている場合もあるため、受験会場も併せて各校の募集要項をご確認ください。
帰国子女のお子様を持つご家庭の多くが、国際教育の充実度で学校選びを行います。
現在、日本の学校では多種多様な国際教育が展開されており、海外でのホームステイプログラムや留学制度、海外姉妹校との交流や海外研修など、他にも学校独自の取り組みが多く行われております。
既に異文化での生活を送ってきた帰国子女ですが、日本帰国後も国際教育に触れさせたいというご家庭は多いと思います。EDUBALの学校訪問記事では、各校の国際教育を保護者目線で解説しておりますので、ぜひ志望校選びにお役立てください!
海外で生活してきた帰国子女にとって、いきなり始まる日本での生活は簡単なものではありません。海外での生活が長いと、学習面だけでなく生活面でも苦労する場合があります。
このように帰国後の生活に不安がある…というご家庭は、帰国子女へのサポート体制を整えている学校を選んでみてはいかがでしょうか?
帰国子女へのサポート体制の充実度は、学校によって様々です。個別でのきめ細やかなサポートがある学校もあれば、早く馴染めるように一般生と同じように扱う学校もあります。帰国子女の受け入れがある=帰国子女向けのサポートがあるという訳ではないため、サポート体制の詳細は各校の相談窓口までお問い合わせください。
進路実績を学校選びの軸にするご家庭も多いです。
大学受験を見据える場合は各大学の合格者・進学者数を、大学の付属校からの内部進学を狙う場合は内部進学率や各学部への進学率を参考に学校選びを行うと良いでしょう。
大学受験に向けたサポートの有無は学校によって異なるため、各学校のHP等をご確認ください。
また海外大学への進学をご希望の方は、海外大学への進学サポートについても学校側にご確認いただくことをおすすめします。
.
★海外子女・帰国子女向け家庭教師の登録数No.1!帰国子女高校受験対策ならEDUBAL
EDUBALは難関大学に通う帰国子女の大学生と、家庭教師を探している生徒様をつなぐオンライン家庭教師サービスです。
EDUBALでは、インターネットのビデオ通話を通して授業を行うため、世界中どこにいても、いつでもご自宅で手軽に指導を受けることができます。また、高校受験を経験している帰国子女の教師も多数在籍しています。
EDUBALなら、こういったご要望にお答えすることができます。
・志望校の帰国入試に向けた指導をしてほしい!
・編入試験の筆記試験/面接対策をしてほしい!
・苦手科目の対策をしたい!
・英検1級/準1級/2級の対策をしてほしい!
EDUBALでは、現在4000人近くの教師が在籍しております。多数の教師が登録しているからこそ、生徒様と境遇の近い教師を紹介することができます。
さらにEDUBALでは毎月、帰国子女高校受験に関するメルマガを配信し、帰国子女におすすめの記事を紹介しております。
受験は情報戦です。周りと差をつけたい!という方は、ぜひこちらからメルマガの無料登録を行ってください!
【2024年度入試】帰国子女高校受験で人気の高校ランキング!
帰国子女枠の高校受験は一般入試よりも本当に有利?帰国子女高校受験を徹底解説!
【実体験紹介】帰国子女高校受験に最適な帰国時期は?経験者が徹底解説します!
この記事のカテゴリー・タグ
下記では、今までEDUBALで指導を受講された生徒様、保護者様から寄せられた声を掲載しています。
EDUBALで家庭教師をつけるかどうか迷われている方は、ぜひ参考にご覧ください。
英検準二級に合格し、また苦手科目だった数学の点数が飛躍的に伸びました。結果が出ているので安心して任せられます。
生徒に寄り添って根気強く教えていただきました。また、普段から励ましや声掛けなど勉強以外のところでも心の支えになり、モチベーションを上げていただきました。試験に向けての励ましやお声がけもいただき、落ち着いて試験に臨むことが出来ました。本当にありがとうございました。
受験した高校は親子そろっての面接なので、子どもの面接の様子を間近で見ることができました。想像していたよりもずっと立派な受け答えができていたので先生の指導によるものと感謝しています。また英作文のほうも内容・構成ともにしっかりしたものが提出できたようです。この度はご指導いただきありがとうございました。。指導の内容のみならず、生き様や学問に向かう姿勢、ご相談に乗っていただいた内容が、きっとこれから何年もキャリア形成に役立っていくと信じています。本当にありがとうございます。
保護者とも綿密に連絡を取り合い、こちらからのリクエストにも快く応じて内容の濃い授業を続けてくださいました。英語の能力も申し分なく、優しく分かりやすい授業だったと息子も言っております。先生のサポートのおかげで、第一希望の高校入試に合格できました。海外生活が長く日本語に不安がある状態での高校受験でしたが、同じような環境で受験をされた先生だからこそ気持ちを分かっていただけたのだと思います。お力添え、本当にありがとうございました。
勉強に対するモチベーション維持が上手な先生です。 生徒のロールモデルとなって指導してくださいます。